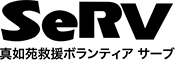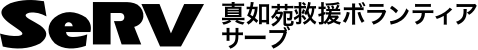情熱シアター

研究者として。
草の根的な交流を欲する
ひとりの人間として。

大阪大学
渥美公秀 あつみ・ともひで
1961年大阪府生まれ。大阪大学人間科学部卒業。フルブライト奨学金によりミシガン大学大学院に留学、博士号(Ph.D.心理学)取得。大阪大学大学院人間科学研究科博士課程単位取得。神戸大学文学部助教授、大阪大学大学院人間科学研究科助教授などを経て、2010年大阪大学大学院人間科学研究科教授。(特) 日本災害救援ボランティアネットワーク 理事長
このページでは、「困っている誰かの為に、何かしたい」という志をともにする方々の、活動に対する熱い思いをご紹介します。
今回は、自ら被災地に入って汗をかくだけではなく、ご自身の研究をボランティア活動の課題解決に活かしている大阪大学大学院 人間科学研究科の渥美公秀さんにお話をうかがいました。
「東京から東北新幹線に乗り、JR八戸駅までおよそ3時間。そこから車で国道45号線を1時間30分ほど走ります。道は途中、海岸と併走しますが、岸からは距離があるため海はほとんど見えません。平成25年度に放送されたNHKの連続テレビ小説「あまちゃん」のロケ地となった久慈市を抜け、さらに太平洋を目がけて南下した先に、総人口4185人※の岩手県九戸郡野田村があります。
※推計人口、2015年5月1日
取材班がこの地を訪れたのは、2015年7月10日(金)です。この日、野田村に建てられた大阪大学のサテライトキャンパスにおいて、人間科学研究科 渥美公秀(あつみ・ともひで)教授が手掛けるフィールドワーク説明会が行われました。野田村と大阪とを遠隔教育システムで繋ぎ、集まった村民の皆さまと6名の大学院生が動画回線を通じて初顔合わせする。彼らはこの夏、野田村に1週間ほど滞在し、村民の皆さまにお話を伺い、その内容を今後の研究成果に生かします。

さて前置きはここまでにして、渥美教授へのインタビューへと移ります。東日本大震災発生後に、渥美教授らはなぜ大阪から一気に北上したのか、話はそこからスタートしました。
あの時、なぜ大阪から、岩手県・野田村へと向かったのか
──2011年3月11日、教授はアメリカ・ロサンゼルスにいらしたそうですね。
渥美教授(以下、渥美):
ええ。フルブライト奨学金の支援を受け、前年10月からカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)に滞在していました。しかし東日本大震災の一報を聞き、すぐさま帰国してNPO法人日本災害救援ボランティアネットワークの事務所に駆けつけました。

──教授は、このボランティア団体の理事長も務めていらっしゃいますね。
渥美:
そうなんです。事務所には、ボランティアの仲間から「ひとまず東京に集まろうとの連絡をいただきました。ボランティア団体が集結してネットワークを組む。その会議に来ませんか? と誘っていただいたのですが、私は断りました。東京で会議しているうちに、現地に行く時間を失うのではないか。何よりもまず現地入りすることが先決だと考えたのです。
──なるほど。
渥美:
同時に、こうも考えました。東京からの人たちは福島、宮城と、南から順に北上してくるに違いない。それなら当面は北が手薄になるんじゃないか、と。
──そうやって地図を追う目は、自ずと北に向いたんですね。
渥美:
ええ。ほかにもこんなエピソードがあります。青森県八戸市には阪神・淡路大震災が起きた年の夏に、西宮市の子どもを支援してくれた人たちがいます。八戸市青年会議所の方々です。彼らは震災の年の夏に子どもたちを八戸市に呼び寄せて地引網を経験させるなど、遊ぶ場所すらなかった子どもたちにかけがえのない夏休みをプレゼントしてくれました。
「あの時、手を差し伸べてくれた方々が八戸市にいる。ぜひ八戸市に行って助けてあげてください」
それは阪神・淡路大震災で助けられた当時の子どもからの申し出でした。彼はすでに20歳を超えていますが、今も感謝の念を抱いています。

──かくして教授は発災から10日も経たずして八戸市に入った、という経緯ですね。
渥美:
そうです。八戸市は大都市で被災地域は限定的でした。地元のボランティアがニーズに対応されていました。「もうちょっと南へ行ってあげて」、そう言われて久慈市に入りました。久慈市も若者を中心に、着々と片付けが進んでいたようにも感じました。「もうひとつ南に行ってあげて」、そう促されて野田村に来てみると......。
──とんでもない風景が待ち受けていた?
渥美:
ドロドロの町でした。当然、中心部にはクルマが入れない。まずは港の近くにあった自分の家を片付けているおばあちゃんに話を聞いて......。野田村には十府ヶ浦という浜辺があります。もちろん有事に備えて防潮林を植えていましたので、町の中心から浜辺は見えなかったそうですが、しかし津波が押し寄せ、木々を一斉になぎ倒し、その木が回転するようにして、家を倒し、町の中心街を根こそぎ持っていった。津波が引いた後、宇部川には流された家屋がそのまま残され、田んぼには、野田港に停留していた漁船が何隻も打ち上げられていました。



深い悲しみを持つ被災者のそばに寄り添う
渥美:
やがて、私たちは野田村に腰を据えるようになりました。私たちの規模では、たくさんの手を広げることはできません。もし野田村の皆さんが受け入れてくださるなら、ここでやりたい。そんな風に、自ずと気持ちが傾いていったんですね。
──なるほど。
渥美:
また、これはウチの団体のスタンスですが、とにかく被災された方々の横にいることを大切にしています。自宅の被災状況を避難所から見に来られた方々と直接話をしながら、『片付けていいですか?』と聞く。決してゴミではないわけですから、手当たり次第に着手せず、ひとつひとつ丁寧に話をして作業に当たることを心がけています。それは被災状況を問いません。

──屋根が崩落している、壁が一部損壊しているなど、いかにも被害が激しいところにボランティアが集中しがちですが、外見上は問題がなさそうな家屋でも、外から見えないところで泥を片付けているかもしれない。そのように判断されたんですね。
渥美:
その通りです。ですから、私たちの団体は戸別訪問を一生懸命に展開しました。西宮から持参した菓子と飲料水を渡し、「どうですか?」と声をかけるんですね。どっから来たん? と聞いてもらえたら、ちょっとだけお話して。「また来ます」と言って長居をしない。そんなことの繰り返しです。

──頼まれればすぐに人員を出せる体制を取りつつ、まずは地元の皆さんに信頼してもらうことを優先したのですね。
渥美:
日本災害救援ボランティアネットワークなんて、立派な名称が付いていますが、野田村では誰も知らないわけです。そのうえ、なんで関西からわざわざ来ているのだろう? って思うのが普通でしょう。周りは東北各地のボランティア団体ばかりなのですから。
──有事とはいえ、すぐさま胸襟を開いてもらうノウハウなどなく、丁寧に、丁寧に話しかけ続けることしかない、ということでしょうか?
渥美:
はい。我々は片道18時間かけて現地入りするバスのなかで、また現地に入った後もミーティングなどを通じて、ボランティア全員が同じ思いを共有します。日本災害救援ボランティアネットワークのスタッフは皆、被災者です。それゆえ個人の実体験を含め、これまでのボランティア活動の現場で見聞きしたエピソードをちょこちょこと喋るんですね。
「ボランティアかて、何してあげるとか、そんなことやないんよ。横にいるだけでいいんや」
そんな気持ちの部分を伝えていきます。皆さん助けたい思いで参加しているから、ついつい手を出そうとする。当時は久慈市内のホテルに戻り、夜遅くまで話しました。そこで感情が溢れ出し、泣き出してしまうボランティアさんもいます。それでも丁寧にフォローして、明日はこういうやり方を試しましょうとか、解決策を見出していく。現場は計画通りには進まず、気持ちと気持ちのぶつかり合いです。

渥美教授の情熱、そしてボランティアの未来
──渥美教授は、なぜ熱心にボランティア活動に取り組まれるのですか?
渥美:
本音を言えば、阪神・淡路大震災で生かされたからではないでしょうか。
あの震災で、私は死ぬ側だったかもしれません。ところが、あの時たまたま生きる側となり、家族を含めて無事だった。だから何に対してかは分からないけれども、どこかでお返ししなくてはいけないという思いがあるんです。

あの時、神戸大学は38人もの学生を亡くしました。私の住まいがあった西宮市の被害も甚大で、近所では通りを挟んだ向かいの方が亡くなりました。当時、死をとても近くに感じたことを鮮明に記憶しています。もしもあの時......、多くの方々が命を落とし、それがなぜ自分ではなかったのかが、説明つかないんですね。
──渥美教授は、当時30代。アメリカ留学から戻り、神戸大学文学部の助教授職に就かれたばかりでしたね。
渥美:
はい。駆け出しの大学教員だったからこそ、何かしら動こうとする方向に気持ちを傾けることができたのだと思います。
──教授は「グループ・ダイナミックス」をボランティアの活動現場に活かしているとうかがいました。
渥美:
ええ。グループ・ダイナミックスの定義は"研究者自身がさまざまなコミュニティや組織といった現場に入り込み、現場の当事者と一緒に現場の改善を行っていく実践的な学問"です。私は阪神・淡路大震災で被災者となり、同時にボランティア活動を進めるなかで、このグループ・ダイナミックスの立場から、ボランティアの現場に貢献しようと考えるようになりました。
──先ほど、渥美教授を慕うゼミ学生に話をうかがいましたが、彼はこのように述べています。
「データをとって、対象者を平均化して......、などといった手法ではなく、渥美教授の場合は自分自身がフィールドに入り込む。授業でも"分かりやすい形"で"(被災者にとって)意味のあることをやるべき"と重ねて強調しています。そういう実践的なスタンスに僕はとても惹かれました」
渥美:
そうですか(笑)。とても嬉しく思います。


──この質問を最後にします。ボランティア界の最前線では、いま岐路に差しかかっているそうですが、それは具体的にどのようなことを指しているのでしょうか?
渥美:
被災者のもとで草の根的に顔の見える活動をする立場と、政府、経済団体らとともに経験、技術をもったボランティアを社会の仕組みとして位置付けようとする立場です。その実、このふたつは同じ目標を目指していますが立場、方向性は異なります。ボランティアの現場ではたびたび社会問題に突き当たりますが、それをその場、その場で対応するのか、それとも問題を生み出している制度自体を変えようとするのか。その立場の違いです。
──なるほど。
渥美:
ただ私個人のスタンスとしては、草の根的な活動を続けることが、自分が生かされているという充実感があるように思っています。
渥美教授は、現在もひと月に2回、多い時には複数回、大阪から野田村に足を運んでいます。地元の方々と顔の見える交流をし、さまざまなボランティア活動を進めると同時に、自身の研究と、学生たちの学びをサポートしているのです。大学教授という肩書きからは想像もできない物腰のやわらかさと、人懐っこさ。その人柄に、人の輪が形づくられていると感じました。
野田村の方々は皆、「先生の人柄のおかげだ」と言います。大阪と東北の気質には、かなりの隔たりがあるのではないか? そんな疑念に、渥美教授が躊躇なく、こう答えたのが印象的でした。
「心を開いてもらえるまで、ひたすら傍にいて、そっと話し続けるんです」
本稿の冒頭に紹介したフィールドワーク説明会とは、大阪大学院生によるラジオ番組企画に関する内容でした。学生たちが野田村の皆さまにお世話になるお礼として、野田村で何を感じ何を掴んだのか、それぞれの率直な思いをコミュニティラジオに乗せて発信するそうです。
東日本大震災を通じて、ラジオの有用性が改めて浮き彫りとなるなか、ここ野田村でも2017年春を目処に、地域密着型ラジオ局の開局準備が進んでいます。もちろん、今はまだラジオ放送局として正式に認可を受けていませんから、実際には電波を発信せず、それ以外の方法で番組を配信します。ただ、本物のラジオ番組のように作っていくことが重要と、渥美教授は話します。

「防災と言わない防災」。これは、渥美教授が2001年に上梓した『ボランティアの知 実践としてのボランティア研究』(大阪大学出版会刊)に書き記されたキーワードです。大義をかざして災害対策を進めるのではなく、知恵と工夫で防災・減災行動を生活のなかに溶け込ませる。野田村でのラジオイベントも、同じ発想で導かれたものに違いありません。それがグループ・ダイナミックスの解決力なのでしょう。