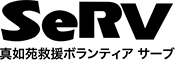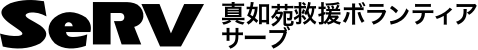情熱シアター

徹底した現場主義。
災害ボランティア最前線で積み重ねた
知見、そして仲間との信頼。

全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動振興センター
副部長
園崎 秀治 そのざき・しゅうじ
社会福祉法人全国社会福祉協議会(全社協)全国ボランティア・市民活動振興センター副部長。1994年に全社協に入局。総務部、全国ボランティア活動振興センター、法人振興部を経て、2014年に現職に就任。全国のボランティア・市民活動センターを通じたボランティア活動の基盤づくりや、福祉教育や災害支援等を通じて、幅広い関係者とボランティア活動の推進に関わる。
このページでは、「困っている誰かの為に、何かしたい」という志をともにする方々の、活動に対する熱い思いをご紹介します。
今回は、災害発生時にはいち早く現地に入り、必要な支援内容を見極めて支援者の派遣や後方部隊に繋ぐ、全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動振興センター副部長 園崎秀治さんにお話をうかがいました。

東京・霞が関官庁街の一角にある全国社会福祉協議会のオフィス。そこに園崎秀治さんを訪ねたのは、2015年10月半ばのことでした。北関東一帯に大きな爪痕を残した台風18号による豪雨災害の対応に追われている大変お忙しい状況でしたが、園崎さんは終始穏やかな笑顔で、お話をきかせてくださいました。
災害ボランティアの心の在りようとは?
──本日は、よろしくお願いします。はじめに園崎さんがボランティア活動に積極的になっていったきっかけを教えていただけますか?

園崎秀治さん(以下、園崎):
災害の現場は、修羅場です。現地では人間の心の奥深いところや欲望の渦を見せつけられるようなことも経験します。しかしそんな中でも、支援者たちの熱い思いとでも申しましょうか、仕事として決められたことをやっていればいいと考える人は誰一人いないんです。皆、何かしら被災地で大変な思いをしている人たちの役に立てたらという一心で被災地に向かいます。
その気持ちに触れ続けてきた影響は大きいですね。皆、自分の仕事だけで手いっぱいの中、業務の調整をしてでも被災地の支援に行こうという人たちが大勢いるんです。その思いに感化されてきたのでしょう。
──そうなんですね。ところで "災害の現場は修羅場"とおっしゃいましたが、そういう場に必要とされるものとは、どのようなものでしょう?
園崎:
2015年9月に起きた鬼怒川決壊による浸水被害で、"支援P"(※後述)のメンバーに茨城県常総市をはじめ、栃木県や宮城県の被災地に入り続けてもらっています。その常総市の災害ボランティアセンター長から言われたことが印象に残っています。
センター長曰く、「"支援P"の人たちはとても不思議だ」と。「職業も違えば、それぞれ異なる地域から集まっている。しかし、ある一定の共通項がある。それは立ち振舞がゆっくりしていることだ」と。そして「被災地で、どうしてそういう状態を保ち続けられるのかがとても不思議だ」とも。

センター長はこのように続けます。「非常に落ち着いているから、相談がしやすい。
しかし、ひとたび相談すると、あっという間に結果が返ってくる。何かを依頼すると、すぐに調達して持ってきてくれる。動きがゆっくりしているのに、反応が早い」。
──混乱している現場で落ち着いていらっしゃって、なおかつ反応が早いなんて、すごいことですね。
園崎:
実は、そのスタンスこそが自分たちが目指してきたことです。外部支援者が、現地で一緒になって感情的になってしまっていてはダメなのです。
災害のプロと自称する人たちが、時折、現地で声を荒げている光景を目にします。「俺たちはいろいろ経験してきたのだから、俺たちの言うことが正しい」と、彼らは主張する。それは良くない考え方です。
地元の人たちははじめての対応で、どうするべきか分からず、さまざまな問題にぶつかります。それを見て、「何をやっているんだ?」と思ったとしても、外部支援者は、地元の人たちを支えるために来ているのであり、彼らを批判するために来ているのではありません。ましてや彼らは被災者なのです。被災者でもあり、支援しなければならない辛さがあるのです。それを分かったうえで、接しなければなりません。
■ 2011年4月 東日本大震災 宮古市のボランティア活動


──それぞれの置かれた立場を意識して、接することが大切なのですね。
園崎:
はい。私たちの結論は「地元を尊重して接すること=地元主体」の考え方でした。同時に、相談されればすぐに返す力量を持ち合わせる。自分で返せなくてもチームで返すことができる。ですから常総市のセンター長にそう言われたことは、自分たちがやってきたことが評価されたわけで、とても嬉しかったんですね。
もう一つ、「被災者中心」という言葉がありますが、現地では被災者に感情移入し過ぎてしまう支援者がたくさんいます。すると大変な思いをしている被災者のもとに支援の手が十分に届いていないことに対して怒りはじめる。行政や社会福祉協議会(以下、社協)などを糾弾する立場になっていきます。
でも支援者がそれをしてはいけない、というのが私たちの立場です。外部から来た支援者である限り、常に冷静な目で状況を判断することが必要。支援者が客観性を失い、被災者と同化してはいけないのです。
──全国社会福祉協議会 (以下、全社協)では、ボランティアセンター運営者のための研修会を全国で実施されていますよね。SeRVも参加させていただいていますが、主催者として心している事はどんな事でしょうか?
園崎:
例えば、被災地でボランティアセンターを運営したスタッフをお招きして、さまざまな角度から質問を投げかけます。そこで引き出すことの一つは、「こういう支援者がありがたかった」「こういうことを言われたことが辛かった」ということです。また、ご自身がやりきれなかったことなども吐き出してもらいます。
そうした一つひとつが、被災地に行ったことがない方々、ボランティアセンターを運営したことがない方々にとっての知恵や知識となるのです。
■ 2011年4月 東日本大震災 大槌町

災害ボランティアセンター

よく世の中で、訓練と表現しますが、訓練の多くは、前提条件を置き、その動きを模擬的にトレースするものです。いわゆるマニュアル化ですが、それを中心に置かないのが、私たちのポリシーです。
訓練が役に立たないとは申しません。ただ、それは必要なスキルの一部分です。何もないよりはいいけれども、実際に災害が起きた時にはおそらく訓練通りにいかないでしょう。むしろ訓練以外に伝えるべき大切な事柄がたくさんあり、そこで真価を問われることになります。
──支援者同士が意識を共有することも重要なんですね。
園崎:
被災地で活動を共にした人たちとは、ほとんどブレることなくそのまま付き合っています。これは被災地のマジックだとも思います。厳しい状況のなかで時間を共にして、率直に話をして、同じ方向を向き、活動する。そうした後は、以心伝心のような状況が起こり、ボタンの掛け違いが起こらないんです。
被災地で互いを非難し合ってしまう人たちとは、そうはいきません。彼らには相手への否定感があり、こちらも困ったなぁという感情がありますので、関係そのものが作れない。
逆に、被災地で一緒に冷静に同じ方向を向いて話ができた人たちとは、その後、プログラム作りに加わってもらったり、次の被災地に一緒に行ってもらったり。それこそ日々、顔を突き合わせている職場の同僚以上に何か通ずるものがあるようにも思えます。
言い方が悪いかもしれませんが、被災地で行動を共にした"戦友"たちとは、マインドの共有が自然になされる。何らかの関係づくりをしたのではなく、もう直感的に「この人たちとは一緒にやっていける」という思いがあります。
社会福祉協議会と災害ボランティアの関係性
──ここからは歴史をさかのぼってお話をうかがっていきます。社協が災害ボランティアセンターを担うようになったのはどのような経緯があったのでしょうか。

園崎:
まず1995年に起きた阪神・淡路大震災が、ボランティア元年としばしば表現されます。それは「災害が起きると、被災地にボランティア志望の皆さんが向かう」ことが世の中に認識されたという意味での元年です。
1998年には福島県、栃木県、高知県で豪雨による災害がありました。この時「水害ボランティアセンター」という言葉がはじめて使われました。ボランティア志望者は、ボランティアセンターに来て、そこから現場に送り出されるというシステムが確立します。ただし、そのボランティアセンターを誰が担うのかについてはまだ不透明で、やれる人がやったというのが実情のようです。
──ボランティアセンターを継続していくためには、課題が残ったということですね。
園崎:
阪神・淡路大震災以降、災害ボランティアに関わってきた方々の多くは、自分たちならやれるという自負があります。しかし外部から集まってきた人たちですから、地元に精通しているわけではありません。それに、いつかは活動を終えて去っていく身です。被災者支援とは発災直後の泥掻きなどのみならず、長期にわたり被災者に寄り添っていかなければなりません。その意味では、外部支援者がボランティアセンターを担うことには、もともと限界がありました。

そうしたなかで、再び大きな災害に直面したのが2004年のことでした。新潟県小千谷市、十日町市、長岡市などを襲った中越地震です。しかもこの年は、地震が起こる直前にも、台風23号という10月に上陸した大きな台風災害がありました。
──台風と地震、2つの大きな災害が重なったのですね。このとき全国に100カ所近くのボランティアセンターが立ち上がったと聞きました。
園崎:
はい。災害ボランティアセンターの運営支援といっても、限られたメンバーがあちこちに向かっていた状況ですから、災害が同時に多発するとカバーしきれません。しかも最も被害が大きかった中越地方に駆けつけた多くの災害ボランティアによる先陣争いまで起きてしまいました。早い話が、「一番はじめに現地入りしたチームが、自分たちの言うことを聞け!」という主張です。
以上をまとめると、このようになります。
- 外部支援者には時限的な制約がある
- そもそも被災地の地元を担う主体が外部支援者でいいのか?
- 被災者支援に来た支援者同士が対立してどうする?
こうした反省から、ボランティアセンターは誰が担うべきかが本格的に議論されはじめたのです。そんななかで注目されたのが社協でした。社協は、もともとがボランティアを受け入れてボランティア活動へと繋ぐ、ボランティアセンターとしての核機能を持ち合わせていました。
もちろん災害対処のエキスパートではないのですが、社協はすべての自治体に存在し、自治体とも日常からやりとりしていることから、イザという時に地元からボランティアセンターを立ち上げることができるのです。そこで発災時にはノウハウや経験を持った人たちが地元の社協に集まり、一緒に知恵を出し合って災害復興に当たる「協働」でボランティアセンターを立ち上げたらどうか? という見解が固まってきました。

──そういう経緯があったのですね。
■ 2011年東日本大震災 様々なボランティアセンターにて




園崎:
ええ。このようにして、有事に「協働」でボランティアセンターを立ち上げるために、全社協が音頭を取って、平時の準備を進めることになりました。私は2005年のプロジェクトスタート時からの担当者となりました。実際に、本格的な委員会や研修会などもこの年から始まっています。
厳密に言えば、災害ボランティアセンターを社協が担うようになった経緯はもう少し複雑なのですが、それでも中越地震の時には、社協がボランティアセンターを立ち上げたんです。しかし、その当時はノウハウも不十分で、支援者のスキルも含めて現地ではかなり問題が噴出しました。
──ノウハウがないところからの立ち上げは、相当な困難があったのでしょうね。
園崎:
そうなんです。災害に関しては専門的な知識も経験もなかった組織です。ですから「社協にやらせても、どうしようもない」という厳しい意見もありました。それでも「社協がボランティアセンターを担っていくことが、将来的にいいのではないか?」と、そんな意見もあったと思います。
当時の研修会では、災害ボランティアの第一人者(その多くは阪神・淡路大震災からのメンバー)を委員会のメインに据え、講師としてお招きしました。言わば"災害のプロフェッショナル"を招いて、知識の共有を図ろうとしたのです。
災害ボランティアの最前線を歩んできて
──ここまで社協がボランティアセンターの役割を担う経緯を伺いましたが、ボランティアセンターを「協働」で運営するという当初の方法は、その後も継続されたのでしょうか?

園崎:
そうですね、スタート当初は社協に対して厳しい意見を持つ人たちも少なからずいたのは事実です。彼らを巻き込み、たとえ厳しいことを言われても、その批判を甘んじて受けながら、それでも一緒にやってくださいとお願いして。そうやって、だんだんと交流を深めていきました。
一方で、お互いに応援し合い、ずっと一緒にやってきたのが「災害ボランティア活動支援プロジェクト会議」(通称"支援P")です。彼らも2005年から活動をスタートさせた組織ですが、もともとは災害ボランティア活動をどういう形で支援するのがいいのかを検討していた検証委員会のメンバーです。
彼らは、災害が起きた時に手をこまねいていてはいけないと、"検証"から"支援"に名称を改めました。この"支援P"は、私たち全社協もメンバーです。ほかに中央共同募金会、日本NPOセンター、日本経団連1%(ワンパーセント)クラブなどが手を組み、人・モノ・カネを支援していきましょうということで発足しました。
ただ"支援P"は法人格もなければ、代表もおらず、構成団体が出来ることを持ち寄って支援を行う組織です。モノは各企業が支援します。自分たちはモノを持っているから、それを届けたいとする企業が多いのです。行政に送っても倉庫に眠ってしまって届かないことがあり、被災地にコーディネートする人がほしいというのが、企業側のニーズだったのです。
お金については、1%クラブはもちろんのこと、中央共同募金会も災害時のボランティア活動に向けた仕組みを作ってきました。被災地支援のお金は通常、義援金と呼ばれますが、これは被災者に配分される性質のものです。しかしボランティアする側も、お金がなければ活動することができない。そのために共同募金や企業からの活動支援金が必要とされるのです。
そしてセンター運営を支援する人材のコーディネートについては全社協が担ってきました。研修会にいらした志が高い方々を災害発生時にお声掛けして、現地のボランティアセンターに入ってもらう。しかも場数を何度も踏み、さまざまな知見がある人たちを送ることによって、刻一刻と状況が変わるなかで、次に何をすべきかのアドバイスができるようにもなる。そうした一連のコーディネートが、私の "支援P"における運営支援者を派遣するという役割です。結果的にそのことによって、私が災害ボランティアに関わるあらゆる人と繋がるようになっていきました。
■ 2011年 東日本大震災 様々なボランティアセンターにて




──そういう経緯があったのですね。
最後に、園崎さんの活動に対する思いを、あらためてお聞かせください。
園崎:
"支援P"における人材調整については、この10年間の多くは、私が担い続けてきました。そのためには、初期の被災現場における支援内容の見立てがとても重要であると痛感しています。
現地の状況を見て、ボランティアセンターを立ち上げたり連携したりする関係者と会い、行政の方々ともお会いします。そうやって多くの人たちと話をして、どういう体制で臨もうとしているのかを知り、そこにはどういう支援が必要なのかを見極めて帰ってくる。その情報をスタンバイしている方々に報告して、こちらも体制をつくり、外部支援をスタートさせる。そういう意味で私は先遣としての役割の比重が大きいです。
全国段階でどうしてそこまでやるんだ? とは言われ続けてきました。全社協というのは、現地から見ると遠い存在のようで、何も霞が関から離れなくても、通信手段を用いて連絡を取り合いさえすれば事は済むわけで、誰からも怒られないのかもしれない。ただ、それではきちんとした見立ての元での支援活動ができないというのが、私が被災地に足を運び続けて思うことです。
現場がいま何に苦しんでいて、何を欲しているのか。キーパーソンが誰で、その人には何を伝えて何をつなぐのか。地元がなぜそういう判断を下すことになっているのか、その背景には何があるのか。そうした微妙なニュアンスを含む情報を肌で感じなければ、見当違いの支援になる恐れがあると思っています。
■ 2011年 台風12号の被害による災害ボランティアセンターにて
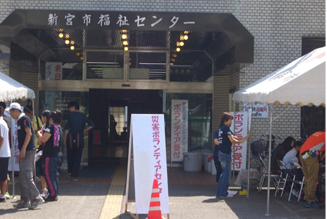



園崎さんは中越地震が起きた翌年、2005年に全社協の全国ボランティアセンター・市民活動振興センターの担当となり、東日本大震災対応までの7年間を災害ボランティアセンターの最前線で過ごされました。そして約2年間の他部署での業務を経て、全国ボランティアセンター・市民活動振興センターの副部長に再び着任。災害ボランティアの現場における園崎さんの活躍が期待されているのでしょう。 「災害にはマニュアルはないし、シナリオもない。毎回、行って当たって砕けろ、みたいな感じなんです」と、園崎さんは話してくださいました。その一方で「自分にはたくさんの仲間がいるから乗り切れる」とも......。

「大きな問題が自分のところに降ってきて、ひとりでは抱えきれないと思っても、片っ端からいろんな人に相談すれば、誰かしらが助けてくれる」この気持ちが、園崎さんの背中を後押ししているのだな、と思いました。
私たちの質問に対して終始、真っ直ぐに答えてくださった園崎さんの姿がとても印象に残りました。「自分の立ち位置でできる限りのことはやる。現地に行ったからには、必ずそれを活かした支援をする」。園崎さんからは、その覚悟が感じられました。